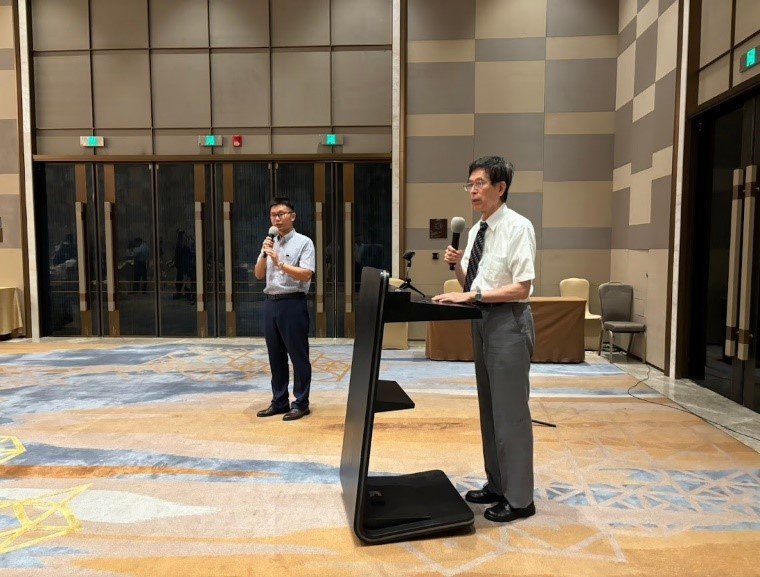【中国視察報告②】危うくなりかけた中国経済の行方 - 習近平の改革はむしろ規制の強化か? - 24.08.06
私は、7月の10日間の訪中で、今は俄か中国ウォッチャーの一人となっている。アメリカは今大統領選で、バイデン大統領が戦列から離れ、副大統領のハリスが代わりの民主党の候補になった。こちらは11月の選挙を見守るしかない。それに対して中国は、2022年憲法を変えて3期目の習近平がどのように舵取りしていくかしっかり見定める必要がある。
アメリカも太平洋を隔てた隣国ではあるが、中国はずっと近くの国である。覇権主義国で政治的な血はロシアに近くとも、経済的には日本との相互依存関係が定着した国であり、日中両国とも相手国なしではやっていけないほど関係が深化している。今後の日中経済的関係は深まることはあっても、薄くなることはあるまい。
<2つの政治外交課題>
しかし、両国間には暗雲がたちこめている。
第一は台湾有事である。日本のみならず、国連もアメリカも中国は一つと認めており、台湾問題は理屈上は中国の内政問題に過ぎず、日米とも簡単には口出しできない。武力侵攻の抑止のための、外交はいくらでもできるが、直接手を出せない。先日、台湾では中国の突然の攻撃を想定して避難訓練が行われたが、日本は米韓はもちろん、他の東南アジア諸国やEU、豪州とも連携して中国の暴走を許さない姿勢を示し続けなければならない。
二番目は尖閣諸島を巡る、領土・領海問題である。こちらは直接の当事者同士であり、日本外交の手腕が試されるところである。中国側の領海侵犯は確信犯であり、軟弱な態度は示してはならないが、だからといって尖閣諸島の突然の国有化といった際どいことを2度としてはなるまい。中国を徒に刺激するだけである。
<立ちはだかる外国人規制の壁>
以上2つの政治外交問題を除けば、あとは経済関係だけだが、どうもしっくりしない。
その一つは、2014年施行の反スパイ法以降、17人もの日本人が拘束されている。次がフランスなど10数か国に与えたビザなし観光を日本に認めていないことである。ほかに短期商用等一次査証(シングルビザ)も滞っているという障害になっている。
23年には、22年に比べて日本の対中投資が64.1%減少した。大きな要因として自動車メーカーが中国産EVに押され、ガソリン車が不振となり、中国から撤退し始めたことがあるかもしれないが、上記の細かい手続き上の問題もあり自業自得の面もある。だから我々訪中団には、4都市(北京、天津、淮安、常州)とも、日本への投資期待の大きさからか、日本語のきれいなパンフレットを作成して投資拡大に並々ならぬ決意を示していた。巻き返しに必死なのが肌で伝わってきた。
<やっと動き出した自民党>
与党自民党は、台湾の新総統 頼清徳の就任式には30人もが大挙して出席した。これに対して、中国は台湾を不可分の領土とする「一つの中国」原則に違反すると抗議した。一方、コロナで中断した日中関係は冷え切ったままである。しかし、放っておいては一大事である。ここにきて我々が帰国した1週間後の7月19日には森山自民党総務会長が訪中し、王毅外相(兼中国共産党政治局員)とも会談。劉建超党中央対外連絡部長(今回の我々訪中団の受け入れ先、5月には訪日)とも会談、2018年以降途絶えている「日中与党交流協議会」の年内再開を準備すると説明した。となると我々訪中団は、森山訪中の露払いの役割を果たしたのかもしれない。
二階元幹事長が引退を表明し、中国とのパイプ役がなくなってしまったからである。
<海江田万里の著作は良書の筆頭>
野党側では、中国通の海江田万里衆議院副議長が同時期に訪中した。私は、彼の分厚い「中国を読み解く」という、1949年以降の中国政治本を訪中にあわせて俄か勉強よろしく慌てて読んでいた。国会議員の著書でこれだけ精緻な本にはお目にかかったことがない。訪中前で必要に迫られたとはいえ、本当にためになる良書だった。大まかな中国の流れは承知していたが、血塗られた中国共産党の内部抗争、特に毛沢東のライバル潰しの権謀術数が赤裸々に書かれており、読み進むうちに恐ろしくなった。
<急成長の光と影>
それに比べれば、今はのどかといえよう。
第20期中央委員会第3回総会(3中総会)は2029年共産中国建国80周年(習政権の任期が切れる2027年の2年後)までに、改革案を完成させるという新しい目標を設定した。
今回の訪中は、全て中国政府が丁寧にセットしてくれたものであり、当然「表」の部分しかみていない。EV(電気自動車)、リチウム電池(この関係の企業は視察先にはなかった)、太陽光発電関係機材という新しい三種の分野は、世界最先端を行っており、経済規模で米国を超えるという目標も近々達成できそうな雰囲気が漂っていた。
<顕在化する不動産不況、格差、少子高齢化>
ただGDPの4分の1を占める不動産業の停滞は、どうも深刻なようだ。高速道路脇や大都市の周辺はみな同じ高さ、同じ造りのアパートがたくさんあり、はたして人が住んでいるのかと疑問に思うこともあった。建設途中でほったらかしにされたような現場もみられた。過剰生産は工業製品ばかりではなく、住宅建設も同じようだ。中国を逆撫でするようだが、蘇州事件は、国内の不満の表れかもしれない。
会見(各市の共産党幹部との会談)で、自ら述べていたが、貧富の格差、東部と中・西部の格差と少子高齢化は心配のタネになっているようだ。特に一人っ子施策の余韻が冷めやらないようで、IT化が進み、人手がかからないようになっているというのに、14億人の人口大国も人手不足だという。外国からすると、人手が足り、これ以上生産されてはたまらないのだが。
<中国には頑張ってほしいと願うばかり>
「中国式現代化」(つまり資本主義とは違う仕組み)「新質生産力」といった、今回のコミュニケで採択された言葉も盛んに飛び出しており、改革者として鄧小平と並んで称される習近平が、今後どういう改革をして中国を引っ張っていくのか、興味と心配が尽きないところである。